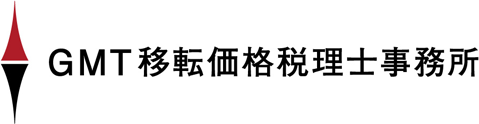本稿の概要
本稿では、ヒアリングから課税に至るまでのステップとともに、各ステップにおける対応方法について解説します。すべてのステップがすべての調査で行われるわけではありませんが、対応に当たっての考え方などご参考になれば幸いです。
ヒアリングの実施
調査官は、移転価格調査の実務②でお伝えしたような基本的な資料を見た上で、資料に関する疑問点や、資料では分からない内容を確認するため、ヒアリングを行います。ヒアリングの内容については、主に国外関連者と取引を行う製品や役務の内容説明や、海外子会社がどのような活動を行っているかなどを聞くこととなります。合う程度は経理部門等で対応することもできますが、海外子会社の詳細な活動内容については、現地に出向していた責任者や、営業担当などが対応することも多いです。また、開発内容についての説明を求められた場合には、開発部門の人員が対応することもあります。
対応方法
日本での税務調査においては、日本側の利益配分が少なすぎる又は海外子会社への利益配分が多すぎるのではないかという主張を受ける可能性が高いものと考えられますが、その根拠として日本本社の高い技術力が収益に貢献していることや、海外子会社の販売先がほとんど日系企業の現地法人などである場合に、日本の営業活動に基づく顧客網が重要な無形資産となっていることなどの事実関係を確認したいものと考えられます。当然、事実に基づいて説明を行わなくてはなりませんが、説明の仕方によっては自社の技術力を過度に誇張してしまったり、日本本社の活動内容の重要性を事実よりも大きく説明してしまうと、調査官に誤解を与えてしまう可能性があります。調査官側も、日本側の帰属利益が大きいことを主張するには、そのような証言を取りたいインセンティブもあるため、お互いに事実誤認が無いよう注意が必要と考えられます。
工場見学
海外子会社の活動内容を把握するにあたり、製造子会社が日本の工場と同様の製造工程を行っている場合などは、日本の工場を見学することで、海外子会社の工場活動内容の説明を求めることもあります。
工場見学の目的は、海外子会社の活動内容を把握するだけではなく、日本でつちかわれた技術がそのまま海外に持っていかれているのかどうかや、日本の工場と海外子会社の工場との違いを確認することで、日本から海外子会社への技術移転の有無や程度を検討する材料ともなります。特に日本の工場をマザー工場として、設備等のレイアウトや工程の手順がそっくり同じであれば、全面的な技術の供与が明白であると考えられます。反対に、海外子会社の工場が、現地人員による改良・改善により、日本の工場よりも優れた内容になっているような場合には、そうした生産技術の改善に対する利益の帰属も検討しなければならない可能性もあります。
対応方法
前述の「ヒアリングの実施」への対応と同様に、税務当局としては日本本社の収益への貢献度の高さについて、事実関係の確認をしたいインセンティブがあることから、製造工程についても日本の技術力の高さを過度に誇張して誤解を与えないように注意が必要です。また、海外子会社の改良・改善活動などがあれば、その内容も含めて正確に説明し、事実誤認が無いようにすることが重要であると考えられます。
中間意見の提示
ある程度事実関係を把握し、それを損益情報と照らしたところで、海外子会社への利益配分について問題があるか否かを中間意見として税務当局の見解が提案されます。問題なしと判断されれば、後述する「調査終了の手続き」のとおり更正または決定(課税)しない理由を明確にしたうえで調査を終えることとなりますが、申告内容や海外子会社との所得配分について問題があると判断された場合には、その問題点について税務当局の見解を口頭により説明され、場合によっては、具体的な課税金額の案が提示されることもあります。ただし、この段階では納税者から反論を行うことができます。
税務当局としては、納税者から説明を受けた内容を前提として課税案を出しますが、税務当局の理解に誤りがある場合もあるため、まずは中間意見として提示をし、事実誤認等があれば、それを聞いた上で、課税判断をしていくこととなります。税務当局が考えていた課税案が事実誤認によるものであれば、課税案の修正又は取消しがなされることもあります。税務当局としても、事実誤認のまま課税をしてしまうと違法な課税となってしまう恐れがあるため、まずは課税案を提示し、納税者の理解が得られるよう議論がつくされます。
自らの取引が正しかったと考える納税者と、税の取り漏れを防ぎたい税務当局との間では、同じ事実関係に対しても解釈が異なる場合もあります。また、移転価格税制の法解釈が異なることもあることから、特に課税金額が大きな事案においては税務当局の主張と、それに対する納税者の反論で議論が長引くケースが多くなっています。
対応方法
税務当局から移転価格の設定に問題があると主張された場合、自社の価格設定ルールが適正であることを反論するには、移転価格税制の理論に基づいて反論書を作成し、提出することが有効であると考えられます。感覚的な主張や、移転価格税制とは関係の無い面からの主張では説得力が低く認めてもらえる可能性は低いものと考えられますが、具体的な数値に基づく分析を含んだ反論書であれば説得力が高く、税務当局の誤認や法令解釈を覆す材料となり得る可能性が高くなります。
また、納税者の主張が聞き入れられず課税に至ってしまった場合、相互協議や不服申し立て等に進むこととなりますが、その際に税務調査でどのような議論がなされたかの情報も必要になることから、税務当局とのディスカッションはできるだけ議事録に残し、当局の主張に対する反論についても、お互いの理解及び備忘記録のため書面で行った方が良いものと考えられます。
修正申告の勧告
税務当局による課税案について議論がなされ、事実誤認も無く、明らかに納税者が移転価格税制に対応していなかったと判断される場合、過去の取引に関して修正申告をすることを勧められます。ここで、納税者として反論の余地が無く、税務当局からの課税案について異論が無ければ、修正申告を行い、過去日本側で漏れていた申告所得について、修正(又は期限後申告)をし、法人税を追加で納付することとなります。
なお、過去の申告漏れを修正する方法としては、修正申告の他、税務当局による更正を行うこともできます。一般的には修正申告が勧められます。税務当局としては、納税者と敵対する立場では無く、納税者の理解を得た上で適正な申告を行うことを求めていると考えられ、更正により課税を行うことはできる限り避けるべきものと考えられます。ただし、修正申告を行う場合には、納税者が同意のもと自ら修正したことを前提としていることから、税務当局に対して不服申し立てや租税裁判を行うことができなくなるため、修正申告の内容が本当に適切なものであるのかどうか、慎重に判断する必要があります。
対応方法
実際の調査の現場においては、税務調査への対応には時間を取られるうえ、精神的に追い詰められるケースも多いことから、早く調査を終えたいために安易に修正申告に応じてしまうケースもあります。また、現実問題として税務調査においては非違する項目について交渉ごとになるケースもあるため、一定の条件のもと修正申告を受け入れるケースもあります。
しかし、移転価格調査に関しては、移転価格税制に明らかに反しているケースばかりとは限らず、税務当局の見解に誤りや事実誤認があるケースも少なくないことから、納得のいかないまま安易に修正申告に応じず、議論を尽くしたうえで判断を行うことが重要であると考えられます。当局の主張に納得がいかない場合や、相互協議及び不服申立を検討する場合には、修正申告に応じずに更正を受けることも選択肢の一つと考えられます。
更正通知
税務当局による課税案について、税務当局と納税者との間で事実関係の解釈や移転価格税制の法令解釈に見解の相違があり、両者の意見が食い違ったまま平行線をたどる場合、納税者が修正申告に応じないとなると、税務当局としては職権によりに更正を行うこととなります。この場合、更正通知書が出され、納税者はそれに従って追徴税額を納付することとなります。
修正申告をする場合と更正を受ける場合とでは、主な違いは納税者が税務当局からの課税案に同意するかどうかについてです。そのため、修正申告の場合には、納税者が課税案に納得していることを前提としているため、原則としては後で不服申し立てや租税裁判を行うことができなくなります。一方で、更正を受ける場合、納税者は課税案に不服があることを前提としているため、課税を受けた後、不服申し立てや租税裁判が行われることもあります。
対応方法
更正通知書には、課税を行う内容と課税金額の計算方法が記載されますので、当該無いようについて事実誤認や計算方法に誤りが無いか、また、不明な点等が無いか確認する必要があります。基本的には更正通知書が出る前の時点で議論は尽くされているはずなので、ここで新たな課税案が出てくることは無いものと考えられますが、更正を受けた後には相互協議又は不服申し立て等を行う可能性があることを前提として、不明な点等が無いようにしておくことが重要であると思われます。
納税の猶予
移転価格課税を受けた場合、速やかに追徴税額の納付を行わなければなりませんが、課税による二重課税を解消するために国家間協議(相互協議)を申し立てる場合には、担保を提供すれば相互協議が合意するまでの間、納期限を延長することができます。
租税特別措置法 第六十六条の四の二
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官(・・・)に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(・・・)は、当該申立てに係る前条第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十六条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第七項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
なお、納期限を延長している間については、延滞税は免除されることとなります。
租税特別措置法 第六十六条の四の二
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
7 納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(・・・)に対応する部分の金額は、免除する。・・・。